近年、働く環境の健全化が求められるなかで、パワハラは見過ごせない社会の課題となっています。
パワハラが引き起こす影響は、当事者だけでなく、職場全体の雰囲気や生産性にも及ぶでしょう。
こうした問題に企業としてどのように向き合って予防策を講じていけばよいのか、本記事では、パワハラの定義と類型から、具体的な防止策、そしてストレスチェックを活用した企業の取り組みについて解説します。
パワハラとは?
パワハラとは、職場での上下関係や人間関係を理由に、業務上必要な範囲を超えて精神的または身体的な苦痛を与える行為を指します。
近年はこの問題に加え、「ハラスメントハラスメント(通称ハラハラ:以下ハラハラ)」という新たな課題にも注目が集まっています。
まずはパワハラの定義と種類、そしてハラハラについてみていきましょう。
パワハラの定義と種類
厚生労働省が示すパワハラとは、以下の3要素すべてに該当する場合を指します。
- 優越的な関係に基づく言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境を害している
また、具体的には以下の6類型にも分類されます。
- 身体的な攻撃(叩く、押すなど)
- 精神的な攻撃(暴言、侮辱的な発言)
- 人間関係からの切り離し(無視、隔離)
- 過大な要求(能力を超えた業務の強制)
- 過小な要求(仕事を与えない)
- 個の侵害(プライバシーへの過度な干渉)
これらは全て、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけではなく、職場の信頼関係を損ねる大きな問題といえます。
ハラスメントに関する最近の課題「ハラハラ」
パワハラ対策が進む一方で、「指導」や「注意」など、本来業務上必要な行為までもがハラスメントと受け取られてしまうケースが増えています。これがいわゆる「ハラハラ」です。
日本のような高文脈文化(表面的な言葉よりも文脈や表情、声のトーンなどの非言語的な点が重視されるコミュニケーション文化)では、発言者の意図と受け手の受け取り方にずれが生じやすいです。
このずれから受け手が「それはハラハラですよ」とアピールすることに、指導する側が萎縮してしまう傾向が強まっています。
ハラハラとなってしまう不安から適切で十分な指導ができないと、職場の生産性や教育の質が低下する可能性もあるでしょう。
企業が取り組むべきパワハラ防止策
ハラスメントのない職場を実現するためには、企業が主体的に対策を講じるのが重要です。パワハラ防止には、制度の整備から日常の意識づけまで、さまざまな取り組みが可能です。
ここでは企業がパワハラを防ぐために行うべき基本的な取り組みを紹介します。
就業規則・制度の整備と相談体制の構築
まず必要なのは、就業規則にパワハラの禁止や対応方針を明記し、周知・徹底することです。あわせて、被害を受けた社員が安心して相談できる窓口を設置し、適切な対応が取れる体制を整えるのも欠かせません。
外部の窓口を併用して相談のしやすさをさらに高めることも、相談体制の構築の一環として挙げられます。
教育・研修を行い、全社員の意識向上を図る
パワハラ防止には、管理職だけではなく全ての社員が正しい知識を持つ必要があります。
新入社員を含んだ全社員を対象にした定期的な研修を通じて、職場で起こりうる具体的なケースや対応方法を学び、ハラスメントへの感度を高めることが重要です。
教育や研修を通して全社員で共通の認識を持つと、相互監視の役割も生まれてパワハラやハラハラが発生しにくくなるでしょう。
ストレスチェック制度を導入する
厚生労働省が推奨するストレスチェック制度は、社員の心身の状況を把握し、ハラスメントの兆候を早期に察知する効果が期待できる手段です。
社員のストレスの変化をストレスチェックによって定期的に測定することで、パワハラやハラハラの実態や、それらの原因となる要素に気づきやすくなり、問題の深刻化を防げる可能性が高まります。
弊社のストレスチェックサービスの活用によるパワハラ対応へのメリット
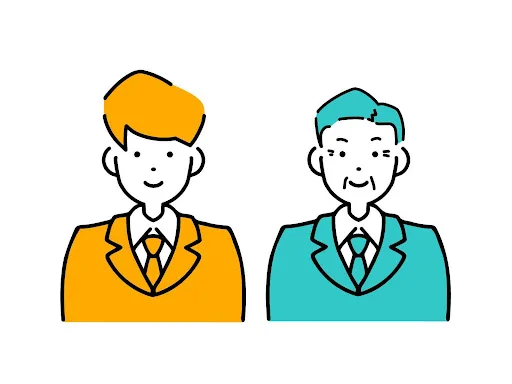
弊社が提供するストレスチェックサービスは、単なる義務化対応にとどまらず、職場の問題点を可視化し、具体的な問題の改善につなげる効果が期待できます。
弊社のストレスチェックを活用し、パワハラの予防や対応を行うメリットを解説します。
集団分析で「パワハラリスク」を評価できる
ストレスチェックの結果を部門単位で分析すると、特定の部門や部署におけるパワハラの可能性や実態がわかるケースがあります。
たとえば、ある部署だけ上司への不満や働きがいの欠如、心身の不調の訴えが目立つ場合、パワハラやハラハラのリスクがあると考えられるケースもあるでしょう。
社員がカウンセラーに相談できる「チャット相談」
弊社のサービスでは、ストレスチェックと連携した匿名チャット相談を導入可能です。
外部のカウンセラーに気軽に相談できる環境が整うと、社内では言い出せない悩みや不安を拾い上げられる可能性が高まります。特にパワハラ被害を受けた社員にとって、社外の専門家へ相談できる場は心の支えとなるでしょう。
自身の言動を見直せる研修プログラムの提供
パワハラを「防ぐ側」の意識の向上も重要です。
弊社では、自らの言動を点検できる管理職者向け・一般社員向けの研修プログラムも用意しています。
アイメッセージ(主語を「私」にした伝え方)などの表現方法や、相手の話を聞く姿勢も含め、コミュニケーション全体を見直せる手法も解説しており、実際に職場で活かせるプログラムとなっています。
ストレスチェックサービスの導入でパワハラリスクを可視化!企業全体に広がる効果

ストレスチェックサービスの導入は、パワハラ対策としての効果が期待できるだけではありません。
企業全体の働きやすさの向上も期待でき、持続可能な職場づくりや生産性の向上にも貢献できます。
最後にストレスチェックサービスを導入すると、企業はどのような効果を期待できるのか解説します。
社員のメンタルヘルス向上により生産性もアップ
定期的なストレスチェックは、社員の心の変化に早く気づく手がかりになります。
また弊社のストレスチェックではチャット相談にも対応しており、ストレスを抱えた社員が外部の専門家に相談できる仕組みづくりも可能です。
社員のメンタルヘルスが安定すれば、業務への集中力や判断力が高まり、チーム全体の生産性も向上するでしょう。
離職防止・採用強化につながる
ハラスメントのない職場環境は、社員が「ここで働き続けたい」と思う理由になります。離職率の低下はもちろん、企業の評判向上にもつながり、採用活動においてもプラスの効果が期待できます。
経営の側面では、離職を防げる点から、人材不足や採用コストの増加を防げる可能性もあるでしょう。
社員が安心して働ける職場は、企業にとっても大きな財産となります。
パワハラ・ハラハラ対応に悩む担当者の方は弊社へご相談を

パワハラ対策は一過性の取り組みではなく、継続的な制度の整備と風土づくりが不可欠です。そして、ハラスメントを「自分とは無関係」と捉えず、誰もが当事者として関わっていく姿勢が、健全な職場文化を生み出していくでしょう。
弊社では、ストレスチェックを起点としたハラスメント防止施策を多数ご用意しています。
相談体制の整備、社員研修、外部相談サービスまで、一貫してサポートします。職場改善に取り組みたいとお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。


